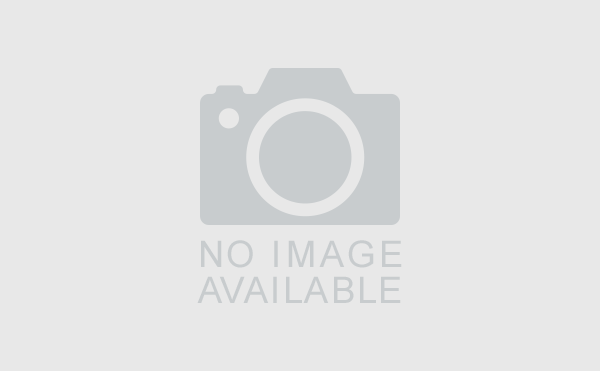林業現場で樹の一生を学ぶ「一本まるごと物語」


企画内容
本来立ち入りできない林業現場で森のリアルが学べる希少ツアーです。
ガイドをしてくれるのは現役のきこりさん。森を守り、育んでいるからこそ話せるネタには引き込まれることでしょう。
地図に無き道を歩き、森の奥まで来たらみんなで一本の木を伐倒します。のこぎりでの伐倒は、なかなかの手ごたえ。次第に樹が揺れ始め、ミシミシミシと音を立てて倒れる瞬間は圧巻です!
伐倒後は、伐倒の余韻とほどよい身体の疲れを感じながら昼食タイム。きこりさんと輪になってきこり飯をいただきます。森の空気も相まって、瞬間パワーチャージ。
午後は、午前中にみんなで倒した木をきこりさんがチェーンソー製材してくれます。自分たちが切り倒した樹が材として生まれ変わる瞬間に立ち会えます。
フィナーレはその材を使って小枝の椅子づくり。樹の表情を楽しみながらお気に入りの一脚をつくりましょう。生木で作りますので、ご自宅にお持ち帰りいただいてからも表情の変化をお楽しみいただけます。

ツアー 行程
9:00 信濃大町駅集合
移動(各自の車orタクシー)
9:30 林業現場にてネイチャーガイド
のこぎりで伐倒体験
年輪観察
12:00 昼食(きこり飯)
13:00 小枝の椅子づくり(お土産としてお持ち帰りいただけます)
15:00 林業現場解散(タクシー希望者は手配致します)
※林業現場は地図に載っておりません。マイカーでお越しの方は当社の車が先導する形でご案内いたします。
| 設定期間 | 通年 |
| 設定除外日 | 12/28~1/5、8/13~16 |
| 最大申込人数 | 4~15名 |
| 大人料金 | 4名 160,000円 5名以上 187,500円 |
| 子ども料金 | 一人 21,000円 |
| こども料金基準 | 小学4年生~中学生 |
| こども料金補足 | |
| 料金に含まれるもの | ガイド料、レンタル料(ヘルメット・のこぎり他)、伐倒する木一本の代金、昼食(きこり飯)代、保険代 |
| 注意事項等 | 実歩行時間目安 1時間、歩行距離目安 2㎞、歩行標高差目安 200m以内 服装:長袖、長ズボン、帽子、軍手 ※植物でかぶれたり、虫に刺されたりするリスクがあるため、肌の出ない服装でお越しください。 ※木工でも汚れますので、気になる方はワーク用エプロンをご持参ください。 持ち物:飲み物、レインウェア、リュックサック(両手が空くように) 雨天時の対応:小雨決行 荒天の場合は、前日17:00までにご予約いただいたお電話番号にご連絡いたします。 ※会場は季節により変更する場合があります。 |
キャンセル規定
予約締切後2日前まで30%、前日40%、当日ツアー開始前50%、無連絡不参加100%
企画実施会社
合同会社北アルプス学びと遊びの旅行社
申込受付期限
2週間前の12:00まで

ガイドは個性豊かな林業従事者のみなさん。愛情たっぷりの森トーク、伐倒の際のプロオーラ、普段とは出会えない職人と出会えます。 


本来は立ち入りできない森林作業道を歩きます。夏は青々とした緑の森、秋は彩豊かな紅葉の森、その時期ならではの自然を堪能できます。 
空を見上げ、どの方向に気を倒したらよいか話し合います。方向が決まったら生きている木に触れ、感謝を伝えてから伐倒開始。ノコギリから伝わる木の生命力、ゆらゆらと倒れ始めるドキドキ感、極めつけは倒れていく「ミシミシ」という音。五感で感じる伐倒です。 
伐倒した木を運び出せるように「枝払い」「丸太切り」といった作業を行い、ロープワークで搬出します。いろんな角度に生えた枝を工夫して切ったり、黙々と丸太切りをしたり、気づけば夢中になってノコギリを動かしていることでしょう。 
パワーチャージできる”きこりめし”。メインは鹿肉がたっぷり。この土地ならではの辛い麴味噌と共にいただきます。季節の野菜が添えられていて、四季も感じられることでしょう。 
本来、伐倒した木は製材所へと運ばれますが、このツアーでは林業従事者がその場でチェーンソー製材してくれます。さっきまで立っていた木が材へと生まれ変わる瞬間を見ると、さらに愛おしさが湧いてきます。